培養肉の技術と効率性
工場式畜産の反対派、あるいは単に食として楽しみたい人々を対象に、いわゆる培養肉(実験室で人工的に培養した肉)で作られた食品が市場に出回るようになりました。植物由来の疑似肉やキノコなどの菌類由来のマイコプロテインと同様に、培養肉でできた食品の生産では、カーボンフットプリントが従来の肉(特に牛肉)の場合と比べてはるかに少なくてすみます。
具体的には、培養肉の生産の場合、従来の食肉生産と比べ、使用する水の量を80%以上、土地の面積を90%以上減らすことができると推定されています。使用済みバイオマスなどの副産物や廃棄物の処分を考慮する場合は、フットプリントの計算全体が多少変わります。
Believer Meats、Ever After Foods、Upside Foodsなどの一部の例外を除き、この潜在的な産業の大半はまだ研究開発段階です。とはいえ、プロセスオートメーションとディスクリートオートメーションのどちらも、こうした培養肉の生産手段の特定とスケールアップに貢献しています。
当然、産業が進歩すれば、そうした自動化が培養肉などの大規模製造の根幹となり、規制上の食品安全に関する要件を満たす上で重要となってくるでしょう。
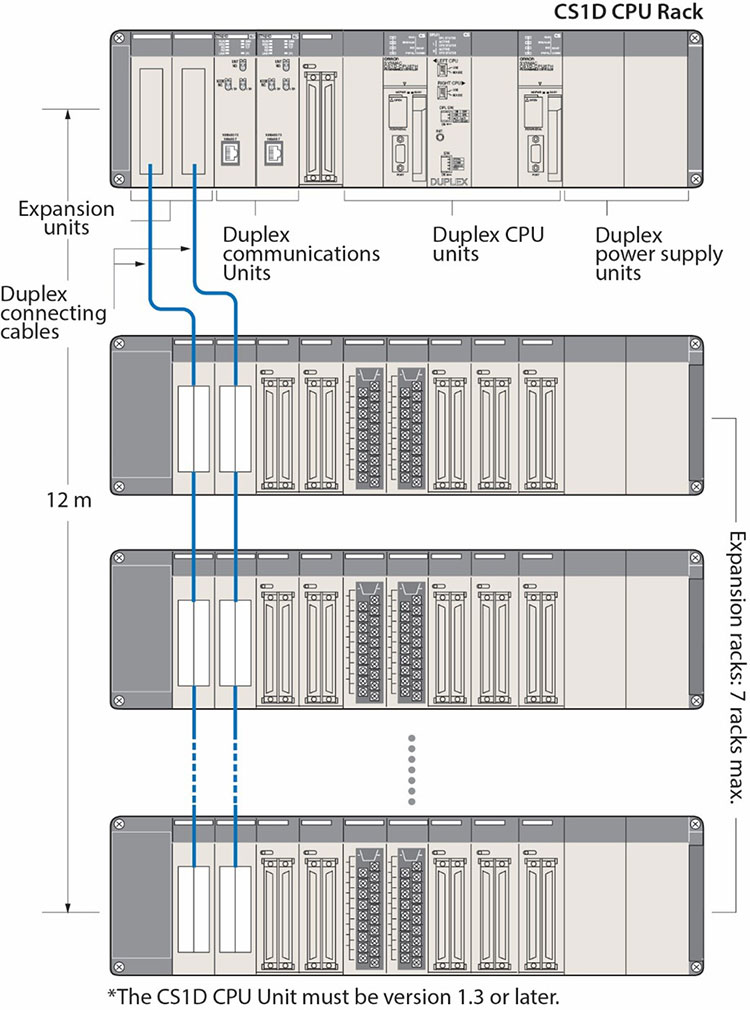 図1:牛肉や鶏肉など、本物の肉のような外観、食感、味を持つ培養肉の生産では、近い将来にPLCとPACによって制御されるプロセスオートメーションとディスクリートオートメーションが実現されるでしょう。(画像提供:Omron Automation and Safety)
図1:牛肉や鶏肉など、本物の肉のような外観、食感、味を持つ培養肉の生産では、近い将来にPLCとPACによって制御されるプロセスオートメーションとディスクリートオートメーションが実現されるでしょう。(画像提供:Omron Automation and Safety)
具体的な手順はさまざまですが、通常はドナーとなる動物から細胞を採取し、一時的に保存します。次に、植物やゼラチンの足場材料、栄養素、細胞分化培地(細胞を筋肉や脂肪の形に誘導するもの)を追加したバイオリアクタ(ビールやワクチンの製造に使われる装置のようなもの)を用意し、細胞を入れて培養します。培養中は数週間にわたり、自動化されたシステムによってバイオリアクタ内の温度、pH、栄養、酸素レベルが厳密に管理され、細胞の成長が最適化されます。
 図2:空気圧を利用した攪拌とデジタルツインモデルを活用した最適化ソフトウェアを採用し、既存の技術を改良したバイオリアクタ。(画像提供: Arc Biotech)
図2:空気圧を利用した攪拌とデジタルツインモデルを活用した最適化ソフトウェアを採用し、既存の技術を改良したバイオリアクタ。(画像提供: Arc Biotech)
食品の安全性を維持するため、培養肉の生産に使用する大規模な自動化アセンブリは、CIP(定置洗浄)プロセスとSIP(定置滅菌)プロセスへの対応が求められます。そのため、他の食品生産設備と同様に、ハウジング、エンクロージャ、容器などは主にステンレス鋼製が使用されます。ステンレスは食品と直接接触する機械部分に使用されるほか、洗浄の際の化学物質、熱、水や滅菌用蒸気に定期的にさらされる装置の耐久性向上にも役立ちます。
 図3:304ステンレス鋼製エアシリンダと303ステンレス鋼製シリンダロッドの組み合わせにより、食品加工装置がさらされる過酷な条件への耐久性を向上させた空気圧シリンダ。(画像提供:Fabco Air)
図3:304ステンレス鋼製エアシリンダと303ステンレス鋼製シリンダロッドの組み合わせにより、食品加工装置がさらされる過酷な条件への耐久性を向上させた空気圧シリンダ。(画像提供:Fabco Air)
また、以下の項目も培養肉産業にとって重要となるでしょう。
• IoTセンサ、I/O、データ取得装置によるバイオプロセスのリアルタイムモニタリング。デジタルトランスフォーメーション(DX)アーキテクチャを備えたクラウドベースのシステムに統合される形態をとることが多い
• ロボティクス(時にはAIベースの画像認識機能によって補完)。細胞選別、播種、サンプリング、収穫、品質管理などの各種作業に応用
• 3Dプリンティング装置。混合した材料を押し出し、特定の肉の組成や食感を再現
もちろん、他の種類の食品生産(野菜や果物の栽培など)においても、かなり前から自動化が進んでいます。こうした装置は、加工や包装の設備に使用されるほか、畑や果樹園、さらには温室や垂直農法でも活用されています。現在の自動化装置がもたらす多くの利点の中でも、傷みやすい野菜や果物をそっと扱うことができる能力が、おそらく最も重要でしょう。場合によっては、機械化効率を考慮し、あざができたり傷が付いたりしにくい穀物や豆類などと同じ方法でこれらの農産物が市場へ運ばれるためです。
野菜や果物は、培養肉や従来の食肉と比べてはるかに低い生産コストで大きな健康効果をもたらします。もしかしたら、私たちはもっと野菜や果物を食べるようにすべきなのかもしれません。

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum






